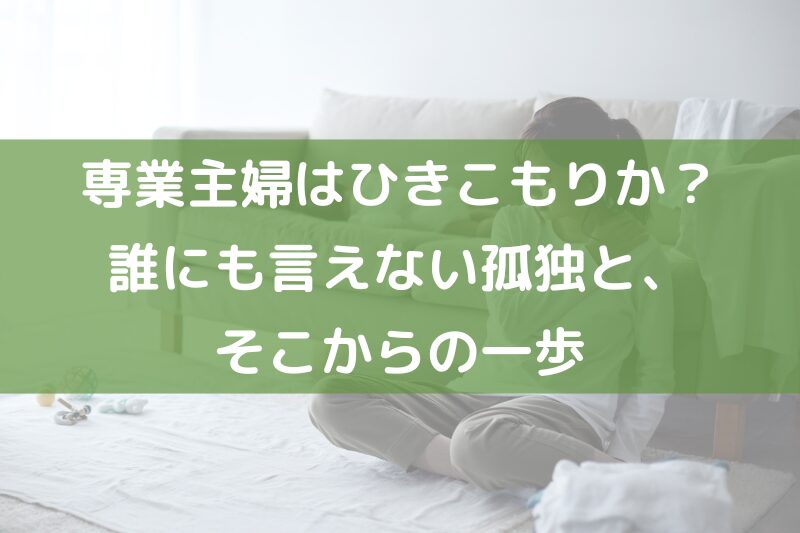こんにちは、あずきママです。
今回のテーマは、「専業主婦のひきこもり」。
最近、ニュースでも話題になっていますね。
今に始まったわけではありませんが、実は今、国の定義でも「専業主婦のひきこもり」が含まれるようになってきているんです。
家事や育児に追われ、社会とのつながりを絶たれたまま、気づけば10年も誰とも話していない——。
そんな現実を抱える女性たちが、今、静かに声を上げ始めています。
私自身も、育休中は社会生活と離れて、孤独感を感じていたうちの一人です。
この記事では、ひきこもる専業主婦たちのリアルな声や、その背景にある家庭・社会の構造を深掘り。
どうして孤立してしまうのか?そこから抜け出すためには、どんな支援が必要なのか?
徹底的にわかりやすく解説していきます。
読み終わるころには、あなた自身や身近な人の「生きづらさ」に、そっと寄り添えるようになるかもしれません。
専業主婦のひきこもりが社会課題として注目される理由

専業主婦のひきこもりが社会課題として注目される理由について、詳しくお話していきます。
①専業主婦もひきこもりと認定される時代
実は今、専業主婦も「ひきこもり」として国の統計に含まれるようになっています。
内閣府の定義によれば、半年以上にわたり仕事をせず、家からほとんど出ない状態は「ひきこもり」と認定されます。
さらに、「家族以外との会話がほとんどない」という状況も含まれています。
このため、家事や育児に専念していても、社会的接点が極端に少ない専業主婦もひきこもりとみなされることがあるんです。
大阪府の53歳の女性は10年間、家族以外とほとんど話すことなく暮らしていたといいます。
ワンオペ育児で精神的に追い詰められても、実家は遠方で頼れず、夫は出張で留守がち。近くに住む義母との関係も良いとはいえず、子育てのささいな悩みを誰にも相談できませんでした。
出典:withnews
こうした「見えないひきこもり」が社会に一定数存在しており、ようやく可視化され始めた段階にあります。
「専業主婦=ひきこもりじゃない」と思う方もいるかもしれませんが、定義が変わった今、社会の受け止め方も変わってきているんですよね。
②見えにくい孤立の実態とは
専業主婦のひきこもりの特徴は、その「見えにくさ」にあります。
表面的には家事や育児をこなしているように見えても、社会とのつながりは途絶えているケースが少なくありません。
「子どもを保育園に送ったあと、家で誰とも話さず一日が終わる」そんな日々が10年続く人もいます。
特に、都市部では近所付き合いが希薄で、孤独を感じやすいという声も多くありました。
また、自分自身が「ひきこもり」であるという自覚がないまま長年過ごすことも、問題の発見を遅らせる要因になっています。
声を上げづらい、理解されにくい、だからこそサポートにもつながりにくい現実があるんです。
これは本当に深刻な課題だと思います。
③社会とのつながりが絶たれる背景
なぜ、専業主婦は社会とのつながりを失いやすいのでしょうか?
理由のひとつは、出産や育児による「自然なキャリア中断」があります。
そこから社会復帰のきっかけを掴めないまま、家庭に専念する日々が続いてしまう。
また、仕事復帰を希望しても「子どもが小さいから無理」と家族に言われ、断念するケースもよくあります。
ある女性は、IT企業に勤めていたがリーマンショックの影響で会社が倒産。
ある女性は、最終的には精神的な負担から家にこもるようになったと話しています。
産休と育休をとったことでキャリアが中断、それでも1年後には職場に戻ったが、合わない部署に戻ったことと育児のストレスからうつ病になって休職。
出典:東洋経済オンライン
仕事に戻れないことが、社会からの断絶感を強めてしまうんですよね。
子育てが一段落しても、「今さら働けない」という心理的な壁が、そのまま孤立へとつながってしまうのです。
私も育休から復職する際には、「社会復帰できるのか?」という不安と同時に、「早く社会に出たい」という気持ちがつよくあったのを思い出します。
④「家にいるのが当たり前」という固定観念
「主婦は家にいるのが普通」——この価値観が、専業主婦のひきこもりを助長しています。
これは本人の意識だけでなく、家族や社会全体が持つステレオタイプでもあります。
主婦仲間の飲み会を開いても「主人がいい顔をしないから」と参加しづらいという声もありました。
島沢さんが働きながら小学生の長男長女を育てていたころ、クラスのママ友同士の飲み会を企画すると、専業主婦の中にはほとんど来ない人や短時間だけの参加者がおり、「主人がいい顔をしない」などと言ったという。
出典:朝日新聞
こうした「夫の目線」が、専業主婦を家庭の中に縛り付ける要因にもなっているのです。
自分の意思で家にいるようで、実は周囲の期待や圧力に応えるために選んだ形だけの「自由」。
この価値観の呪縛は、とても根深いものがありますよね。
もちろん、自ら専業主婦を選んだ方もいらっしゃると思いますが、自分の意に反して家にいないといけない状況にいる方に限っての話ですよね。
⑤夫の価値観や家父長制との関係性
「誰のおかげで飯が食えると思ってるんだ!」という夫の言葉。
これ、いつの時代?と思いますが、残念ながら現在進行形です。
「誰のおかげで飯が食えると思っているんだ!?」と「ザ・昭和」な感じの夫が妻や子にいら立ちをぶつける……などという図式はもう前時代の遺物かと思えば、依然健在らしい。
出典:日経クロスウーマン
専業主婦であることを感謝されるどころか、夫に“養われている”という自責感を抱いてしまう。
そんな家庭内の力関係が、ひきこもりを生む温床になるケースもあるようです。
ジャーナリストの島沢優子さんは、専業主婦の生きづらさを語っていました。
島沢さんは「つまり、家父長制は誰も幸せにしない」と強調。
出典:朝日新聞
夫も「一家を支えなければ」というプレッシャーに苦しんでおり、結局、誰も救われていないんですよね。
家族という単位が、知らず知らずのうちに誰かを追い詰めてしまう。
これはすごく考えさせられました。
ひきこもる専業主婦たちのリアルな声と背景

ひきこもる専業主婦たちのリアルな声と背景について、実例を交えて深掘りしていきます。
①10年以上家族以外と会話がない現実
大阪府に住む53歳の女性は、この10年間ほぼ家族以外と会話をしていない生活を送ってきたそうです。
外出は最低限で、買い物や子どもの用事以外では人と接することがほとんどないとのこと。
「家にいても話し相手がいない」「ひとりで考え込むことが増えて気持ちがふさぎがちになる」と語っていました。
特に、ワンオペ育児を経験した女性たちの間では、こうした孤立状態が日常的に起きています。
夫が仕事で不在がち、実家も頼れない。
気づけば「誰とも話さない日々」が、何年も続いているというのが実態なのです。
それでも女性は「表面上は、ただの主婦」に見えるだろうと話します。「私が10年ひきこもりであると社会の誰も知らない状態です」
出典:withnews
「ただの主婦」に見えてしまうという言葉の裏には、10年という長い時間、社会とのつながりを絶たれ、自分の存在が“なかったこと”のように扱われてきた感覚があるのかもしれません。
家の中で必死に生きてきたのに、誰にも気づかれず、「普通の主婦」として扱われる…それは「無かったこと」にされるような寂しさがありますよね。
心の中でどれだけ葛藤があったとしても、表には出さずに、静かに耐えてきた強さも感じます。
これは、なかなか想像できない現実かもしれませんね。
②「扶養されるだけの存在」への違和感
「自分は扶養されているだけで、社会に何も貢献できていないんじゃないか?」
こう感じる専業主婦の声はとても多いです。
東洋経済の記事では、「扶養されることで自分の存在価値が揺らいだ」という女性の言葉が印象的でした。
「何もしない自分」に我慢ができない。「夫に扶養されている」ことでさらに自分の存在価値が揺らいだ。(中略)結婚して自立したつもりだったはずだ。だが、またも扶養されなければいけない身になったことが、焦りを生み、「敗北感」すら抱かせたのではないか。
出典:東洋経済オンライン
仕事も家事もできなくなったとき、自分の価値を完全に見失ってしまうのです。
扶養される立場にあること自体が、自己肯定感を奪っていく。
それって本当に悲しいことですよね。
家庭という枠組みの中で、役割が失われた瞬間に「空っぽになってしまう」ような感覚——。
この苦しみを、社会はもっと理解すべきだと思います。
③育児・家事のプレッシャーと限界
「仕事をしていないなら家事は完璧にやって当然」という空気。
それが主婦たちにとって、大きなプレッシャーになっています。
ある専業主婦は、退職して家庭に入ったものの、片づけが苦手な自分に強いストレスを感じていたと語っています。
「主婦なんだからできて当たり前」という無言の圧力が、彼女をどんどん追い詰めていきました。
「家にいる=休んでる」って誤解が、まだまだ根強いですが、実際は、育児も家事も24時間営業。
誰かの食事、洗濯、寝かしつけ、何かしらやり続けてるのに、外でお金を稼いでないと「ちゃんとしてない」って空気は理不尽すぎますよね。
「完璧にやれてない=自分がダメなんだ」って思い始めると、自信もやる気もなくなって、どんどん自己否定のループに入ってしまうことってあると思います。
ワーママでも、「休日なのにできていない」というプレッシャーもあるのに、毎日その圧を感じている専業主婦は尚更だと思います。
こういう見えないプレッシャーは、ひきこもりまでいかなくても、心をじわじわ削っていくから怖いです。
自分の限界に気づかずに無理を続けてしまうと、心も体も壊れてしまいますよね。
④母親からの過干渉と自己否定感
これは一例ですが、過干渉な母親のもとで「いい子」でいることを強いられてきた育ち方が、ひきこもりに影響した例もあるようです。
大学生になって髪型を変えただけで、母に泣き叫ばれ、美容院に連れ戻されたという方は、「自分の意志」や「好きなこと」を押し込めて生きる癖がついたといいます。
そのころようやく“自分の意志”に目覚めたんだと思います。それまでは自我を押し込めて生きていた。小さいころから褒められた記憶も甘えた記憶もないんです
出典:東洋経済オンライン
そして、結婚後、専業主婦として生きるうちに、また自我が消えていく感覚に襲われたそうです。
こうした家庭内の抑圧は、将来の生きづらさの根っこになっているのかもしれません。
自分の意志を持つことに罪悪感すら抱くようになることって、実はすごく多いと聞きます。
それが積み重なって、「自分は何を選んでも否定される」「だったら何も望まない方が楽」という思考になってしまうのも無理ないと感じざるを得ません。
そして、結婚して専業主婦になると、社会からの評価軸がなくなり、ただ“誰かの妻”や“母”として扱われることで、また自分が消えていくような感覚に陥るという、考えさせらるエピソードです。
専業主婦のひきこもり支援に求められる新しいアプローチ

専業主婦のひきこもり支援に求められる新しいアプローチについて、具体的な視点からご紹介します。
①「主婦は家にいるべき」という常識の再考
まず最初に取り組むべきは、「主婦=家にいるもの」という固定観念を見直すことです。
家庭に専念することは悪ではないし、尊重されるべき選択です。
ただし、それを“当然”と捉える社会の圧力がある限り、当人にとっての自由な選択にはなりません。
これだけ女性の社会進出が進む中、未だに根強く残る「夫は外で働き、妻は家を守る」という家父長的な考え。
これに縛られている場合、妻は「外に出たい」とすら言い出せなくなってしまいます。
この無意識の価値観を社会全体で見直すことが、支援の第一歩。
それが、専業主婦自身の選択肢を広げ、ひきこもり状態からの脱却を可能にするんですよね。
②地域でのつながりや女子会の重要性
社会との接点を取り戻すには、まずは「人と話すこと」から。
ひきこもりから抜け出す第一歩は、決して「仕事に復帰する」みたいな大きなことではなく、まずは「誰かと会話を交わす」ことだと思います。
そして、身近なところでは、近所の人、保育園の先生、同じクラスの保護者など。
そうやって、“ちょっとしたやりとり”が重なっていくと、自分が社会とつながっている実感がじわじわ戻ってくるのではないでしょうか。
特に子どもがいる人にとっては、保育園や幼稚園での関わりって実はすごく大きな社会との接点なんですよね。
私も、それで救われていたように思います。
また、きっかけとしては、地域の女子会や交流イベントもあります。
たとえば、「ひきこもりUX女子会」という活動では、当事者の女性たちが悩みを共有し合い、安心して話せる場が設けられています。
「今年に入って夫以外と会話したのは、正月に会った親戚と、月に1回通うカウンセリングの先生を除けば、初めてです」
出典:毎日新聞
同じような立場の人とつながることで、「ひとりじゃない」と思えるようになります。
ちょっとした集まりでも、心がふっと軽くなるのではないでしょうか。
③カウンセリングや支援団体の活用法
ひきこもり状態から抜け出すには、専門家のサポートが必要なこともあります。
カウンセリングを受けることで、自分の思考のクセや、家庭内で感じていたプレッシャーに気づけることがあります。
また、「ひきこもりUX会議」などの支援団体では、元当事者のスタッフが相談を受けたり、ステップを踏んで社会復帰を目指せるプログラムを提供しています。
ひきこもり支援=若者だけ、というイメージが強いかもしれませんが、最近は中高年女性にも広がりつつあります。
「話していい場所」があるだけで、本当に救われる気持ちになりますからね。
④行政による制度整備の必要性
専業主婦のひきこもりは「見えにくい」ゆえに、支援制度が追いついていません。
現在、行政の多くの支援窓口は「働き盛りの男性」や「若年層のひきこもり」を想定しています。
しかし、実際には、40代・50代の女性が多く支援を必要としている現状があります。
行政は、専業主婦を“無業者”としてカウントしないこともあり、統計上も見えづらくなってしまうのです。
支援制度の設計そのものが、ジェンダーバイアスに囚われています。
これを打破しないと、専業主婦の声はいつまでも届かないままになってしまいます。
⑤メディアによる正しい理解と可視化
メディアの役割もとても大きいです。
「ひきこもる主婦」のリアルな声を記事やドキュメンタリーで届けることは、世間の理解を深める第一歩になります。
最近では、Yahooニュースや朝日新聞などでも特集が組まれ、少しずつ認知が進んできました。
ニュースを見て初めて知った方も多いでしょう。
でも、まだまだ足りません。
主婦がひきこもるなんて「サボってるだけでしょ?」という偏見は、今でも根強く残っています。
こうした誤解を解き、当事者の心情に寄り添うような報道がもっともっと必要だと思います。
⑥夫婦間の意識改革がカギになる
実は、夫の理解や協力も非常に重要なんです。
「俺が稼いでるんだから、妻は家にいるのが当然」という意識を変えるだけで、専業主婦の選択肢がぐっと広がります。
共働きでなくても、家庭内の役割分担を見直すだけでも、妻の“閉塞感”は和らぎます。
また、ちょっとした「外の活動」を応援してもらえるだけで、外出への一歩が踏み出しやすくなります。
「話を聞いてくれる」「背中を押してくれる」——それだけでも、大きな支援になりますよね。
まずは、一番近くにいる家庭内の理解が、最初の小さな突破口になることも多いんです。
⑦社会全体で「生きやすさ」をつくるには
結局のところ、専業主婦のひきこもりを防ぐには「生きやすい社会」をつくるしかありません。
どんな働き方でも、どんな家庭の形でも、「それでいいよ」と言える空気感。
「家にいたい人はいればいいし、働きたい人は働けばいい」——そんな多様性を認める社会。
さらに、「ひきこもってしまった自分を責めないでいい」と思える価値観の変化も必要です。
誰だって、しんどくなるときはあります。
一度立ち止まっても、また歩き出せばいいんです。
そんな風に、優しいまなざしで見守ってくれる社会こそ、今の日本に一番求められているんじゃないでしょうか。
まとめ
専業主婦のひきこもりは、これまで見過ごされてきた「見えない孤立」です。
家事や育児に追われながらも、社会とのつながりを絶たれたままの生活に、違和感や孤独を抱える女性は少なくありません。
夫の価値観や家父長的な社会構造が、未だに根強く、専業主婦の声を封じ込めてきた背景も見えてきました。
一方で、カウンセリングや当事者会などの小さなきっかけから、再び人とつながる希望も見え始めています。
支援の対象として可視化し、行政や社会全体がサポートを拡充していくことが急務です。
「主婦=家にいるもの」という固定観念から自由になり、もっと柔らかく、優しい社会をつくること。
それこそが、専業主婦のひきこもり問題を解決するための第一歩かもしれません。
私はワーママで、「毎日時間ない」「誰か家事やって!」と正直思うこともあります。
ただ、「働いてるからしんどい」「働いてないからつらい」という、どちら側にも苦しみがあって、それを比べ合わずに「お互い大変だよね」って言い合える社会になれたら、もっと優しくなれるのかなと思いました。
同じ女性として、これからも一緒に考えたい問題だと思います。