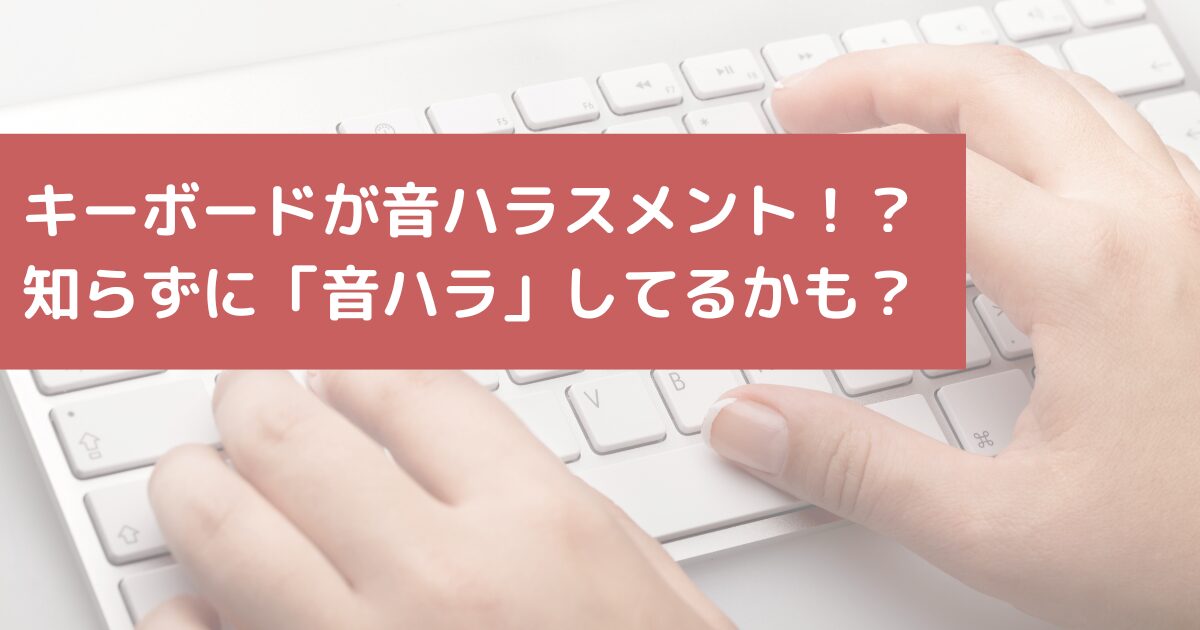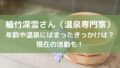皆さんは、「音ハラスメント」という言葉を聞いたことはありますか?
通称「音ハラ」
最近、ニュースで「職場の上司の音ハラに悩んでいる」という記事を見ました。
当たり前ですが、職場にはさまざまな音がありますよね。
同僚のキーボードをたたく音、大声で電話で話す上司の声など、
日常の出来事で特になにも感じていなかったのですが、
仕事に支障が出るくらい悩んでいる人がいるのが現実。
そして、もしかしたら私自身もそう感じさせているのでは?と思うと、少し気になります。
今回は、「音ハラスメント」についてまとめてみました。
★静音キーボードでトラブル回避も1つの方法!
音ハラスメントの具体例と与える影響
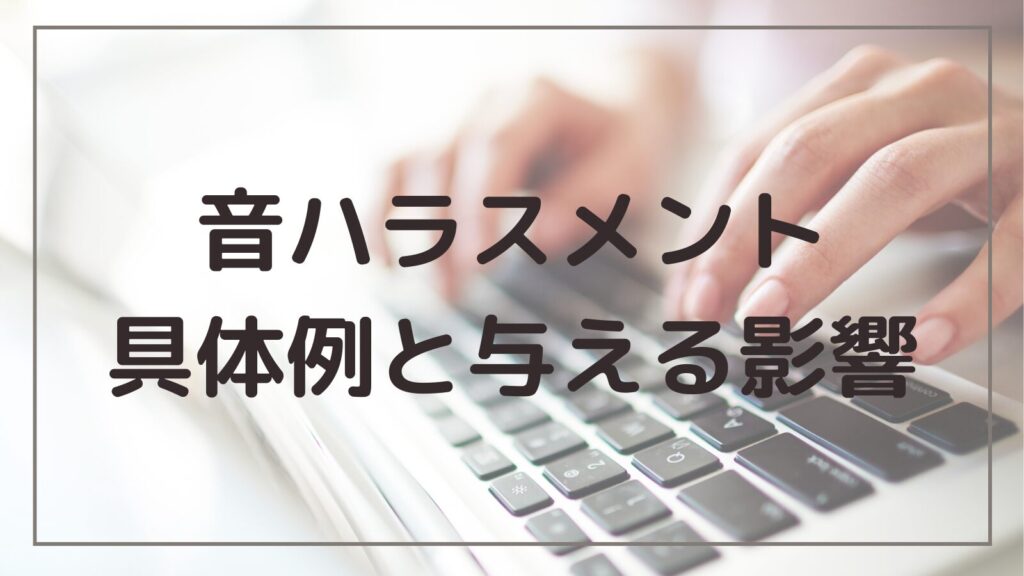
・音ハラの具体例
職場ではあるあるの風景のように感じますが、皆さんはいかがですか?
これを見て「自分もやっている!」という方もいるかもしれませんね。
「私も不快」という方と「そこまで気にしない」方と、人によって感じ方はそれぞれですよね。
ただ、実際に不快と感じる方がいるのも事実。
ニュースやSNSでも「音ハラ」について投稿がありました。
・音ハラが与える影響
1. 作業効率の低下
周囲の音が気になって集中できず、作業効率が下がる。
2. 精神的ストレスの増加
不快な音や騒音を耳にすることで、イライラや不安、集中力の低下を引き起こし、精神的な負担が増加する。
3. 人間関係の悪化
音は人によって感じ方がちがったり、癖などもあるため、直接言い出しにくく、周囲との関係性を悪化させる原因になりやすい。
4. 身体的な不調の発生
長時間の騒音は、頭痛、めまい、耳鳴りなど、身体的な健康被害を引き起こす可能性がある。
「○○ハラスメント」キリがない!?
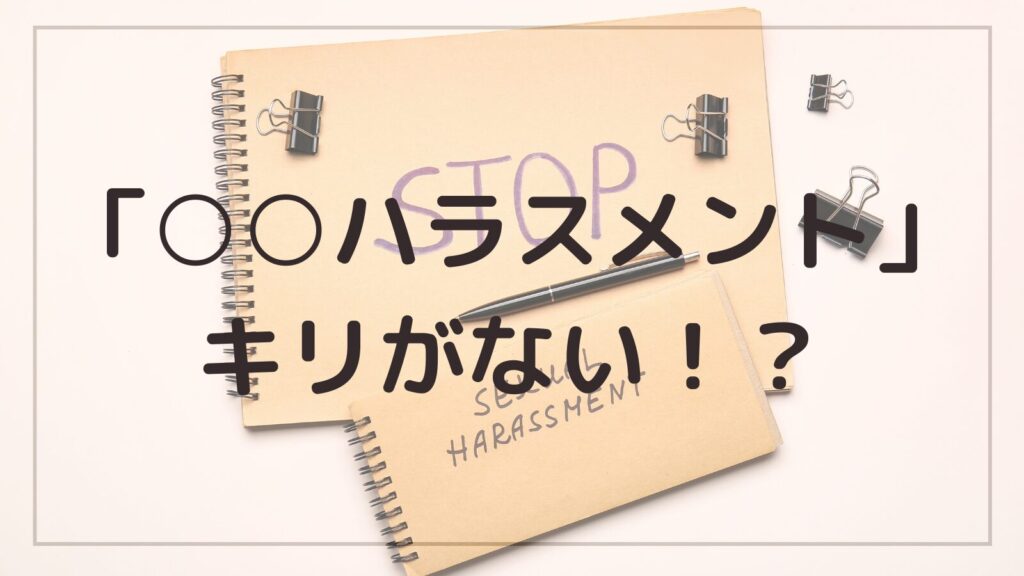
一方で、ある程度の音は「仕方ない」「気にならない」という意見も多数あります。
たしかし、最近は「○○ハラスメント」という言葉をよく耳にしますね。
昔は、「パワハラ」「セクハラ」くらいしかなかった気がするのですが、
「エイハラ(エイジハラスメント)」「アカハラ(アカデミックハラスメント)」など、
私の生活圏ではないからあまり知らないだけかもしれませんが・・・
今回の「音ハラ」も初めて聞きました。
快適な職場環境を実現するために
1. 職場に相談する
社内のハラスメント窓口や信頼できる上司に相談する。
同じように感じている人が多数の場合は、会社としても改善が必要になります。
2. 直接本人に伝える
過剰な騒音で、どうしても気になる場合には冷静に伝えてみる。
体質や癖などもあったり、人間関係にもかかわるので、難しい場合は控えた方がよいかもしれません。
3. 自己防衛
「自分の身は自分で守る」ため、イヤホンや耳栓などを活用するという意見もありました。
もし可能であれな、席を離れて作業するなど、工夫できることはしてもよいですね。
4. コミュニケーションをとって円滑に
お互いに理解しあうため、コミュニケーションで人間関係を円滑にする。
そういった職場では、「○○さん、今日忙しいんですか?タイピングに力入ってますね!」ということも、会話の中でそれとなく伝えられるのではないでしょうか。
また、ハラスメントについても社内で意見交換の場を設け、改善策も見つけやすくなりますね。
まとめ
音ハラスメントは決して他人事ではありません。
職場に限らず、日常生活において音は必ず出るものなので、誰もが被害者になり、加害者にもなりえるハラスメントですよね。
大事なのは、お互いの配慮、これに尽きると思います。
悪気なく無意識に音を出してしまっている人、音に敏感な人、いろんな人が一緒の空間にいるわけなので、互いに理解し合わないことにはうまくいきませんよね。
音について不快と感じるのは人によるので、お互いさまであることを心に留め、快適な職場環境を作っていきたいですね!
★静音ツールを使って快適な職場環境を!